これから宅建(宅地建物取引士)の資格を目指すみなさんにもわかりやすく、宅建を合格するための勉強方法やスケジュール、必要な教材を説明します!
宅建とは
宅建試験は、不動産に関する幅広い知識を問う国家資格試験です。この試験に合格することで、不動産業界でのキャリアの幅が広がります。学生の場合は就職活動に有利に働くことも多々あります。主婦やリタイア層の場合は自分自身の見識を広げることに有効で、人によっては不動産オーナーとして活躍している場合もあります。試験は例年10月に実施され、毎年20万人以上が受験します。
一発で合格できるの?
答えは「はい!」です。正しい勉強方法と計画を立てれば、1回目の試験で合格できます。ただ、合格率は約15〜17%なので、計画的に勉強を進めることが大切です。特に合格者が口を揃えて言うのは「過去の試験問題をたくさん解く」ことが大事です。
ゼロからでも大丈夫?
もちろん大丈夫です!主婦や学生、社会人など、いろんな人が挑戦しています。受験資格は特にないので近年では小学生が合格している例もあります。
とはいっても「勉強することからかなり遠ざかっているけどなあ」とか「あんまり勉強してこなかったし、暗記力がないけど大丈夫かな?」
と言った悩みはありませんでしょうか。結論、大丈夫です。多くの方が同じ悩みを抱えております。一足先に宅建試験を合格していった先輩達も同じだったのです。コツコツ続けることが大事です。
勉強時間はどのくらい?
勉強に必要な時間は300〜500時間くらいです。
- 短期間で頑張る場合: 3か月で合格を目指すなら、1日3〜4時間。
- ゆっくり進める場合: 6か月〜1年なら、1日1〜2時間でOK。
自分に合ったペースで進めましょう!
通信講座と独学の違い
| 項目 | 通信講座 | 独学 |
|---|---|---|
| 費用 | 3〜10万円くらい | 1〜2万円(教材費) |
| サポート体制 | 先生に質問できる | 自分で調べる必要がある |
| 学び方 | 決まったスケジュールで進む | 自分で自由にスケジュールを組む |
| おすすめの人 | サポートがほしい人 | 自分で計画的に勉強できる人 |
どちらを選ぶかは、自分の性格や生活スタイル、費用面を総合的に考えて決めましょう。
独学におすすめの宅建試験勉強法5選
ではいざ独学で勉強しよう!と思ったもののどのように勉強を進めていけばいいのでしょうか?
5つに分けて解説していきます。
1,テキストと過去問の効果的な活用法
宅建試験の勉強で大切なのは、基礎をしっかりと固めることです。まずは分かりやすいテキストを1冊選びましょう。このテキストを何度も読み、内容を完全に理解することを目指します。
次に、過去問を活用します。過去問を解くことで、出題傾向や重要ポイントを把握できます。解けなかった問題は、テキストに戻って復習する習慣をつけましょう。このプロセスを繰り返すことで、効率的に得点力を高められます。
2,科目別の勉強アプローチ
宅建試験は、法律、権利関係、宅建業法、法令上の制限など、複数の科目があります。科目ごとに効果的な学習方法を取り入れることが重要です。
例えば、法律関係の科目では、重要な用語や条文を暗記することが求められます。一方で、宅建業法では、具体的な業務内容や手続きに関する知識が必要です。科目ごとの特性を理解し、それに合った勉強を進めましょう。
3,モチベーションを維持する方法
独学で重要なのは、途中で諦めずにモチベーションを維持することです。小さな目標を設定し、それを達成するたびに自分を褒める習慣をつけましょう。
例えば、「今週は宅建業法のテキストを50ページ読む」といった具体的な目標を立てると良いです。また、合格後の自分を想像することで、学習への意欲が湧いてきます。
4,短時間で効率的に学ぶ工夫
忙しい人には、スキマ時間を活用する方法がおすすめです。スマホの学習アプリを使ったり、単語カードを作ったりして、通勤中や休憩時間に勉強しましょう。これにより、短時間でも集中して学ぶことが可能になります。
5,定期的な進捗確認と模試の活用
勉強を続ける中で、自分が計画通りに進んでいるか確認することも大切です。週に一度は進捗を振り返り、必要があれば計画を見直しましょう。これにより、無理なく目標を達成できます。
また模試はぜひ受けてください。その理由としては3つあります。
- 同じ受験生の中で現在の自分の立ち位置を知ることができる
- 自分の弱点を早期に発見できる
- 試験本番の良い練習となる
まずお伝えしたいのが、「ある程度実力がついてから模試を受けよう」と言ったスタンスはやめた方がいいと思います。結局そのスタンスでいるといつまで経っても模試を受けることはないからです。ですので模試は可能な限り早く申し込んでください。
では模試を受けた方が良い理由を一つずつみていきましょう。
まず一つ目に、模試を受けることで全体の受験生の中での順位がでます。受験生のレベルを客観的に認識できます。自分は良いペースで勉強できてるな、またはちょっと遅れているな、と言った具体です。ただ、決して一喜一憂しないでください。順位が悪ければその分勉強のスケジュールを見直せば良いのです。
二つ目に弱点を早期に発見することで、勉強の偏りを修正することができます。と言うのも勉強をしているとどうしても得意、不得意の分野がでてきます。人は自分が可愛いもので、得意な分野をより勉強し、苦手な分野は知らず知らずのうちに避けてしまうものです。特に独学での勉強ではその傾向が顕著となります。模試の結果が発表される際、答案の傾向が記載される模試もあります。それをみて、苦手な分野を認識し、勉強スケジュールを修正しましょう。
三つ目に本番の練習となることです。実際の試験は想像以上に長く感じ集中力が切れる人もいるでしょう。また人によっては時間が足りず、非常に短く感じる人もいるでしょう。実際に模試を受けることで自分の感じ方を認識し、本番に望むようにしましょう。あくまで私の感じ方ではありますが、時間が足りなく感じました。日頃の勉強でも問題を解く速さを改善しよう、と意識した結果、本番では15分以上時間が余りその結果見直しに十分に時間を割くことができました。
勉強スケジュール
短期間での合格を目指すなら、1日3〜4時間の集中した勉強が求められます。この場合、1ヶ月目は基礎知識の習得、2ヶ月目は過去問演習、3ヶ月目は総復習に充てると効率的です。
長期間の計画を立てる場合は、1日1~2時間のペースでも無理なく進められます。学習期間が長い分、復習に時間をかける余裕が生まれます。
例: 6か月で合格するスケジュール
- 1〜2か月目: 基礎を固める(本を読む、動画を視聴)。
- 3〜4か月目: 過去問を解く(間違えたところを復習)。
- 5〜6か月目: 模試形式で練習する。
計画を守るために手帳やアプリを使うのもおすすめです。
独学で宅建合格を目指す際の注意点3つ
独学のデメリットとその対策
独学の最大のデメリットは、分からないことが出たときに解決しにくい点です。これを克服するためには、インターネットやSNSを活用して情報を調べたり、同じ目標を持つ仲間を見つけると良いです。
また、一人で学ぶことによる孤独感もデメリットと言えます。これに対しては、オンライン勉強会に参加したり、学習の進捗を誰かと共有することで、やる気を保つことができます。
よくある失敗例と回避方法
独学でありがちな失敗は、計画が曖昧なまま勉強を始めてしまうことです。これを防ぐには、具体的な学習スケジュールを立てることが大切です。
例えば、「1週間でこの章を終わらせる」「毎日30分間は過去問を解く」など、具体的な目標を設定すると効果的です。また、焦らずに少しずつ進めることで、挫折を防ぐことができます。
試験直前の注意事項
試験の直前には、新しいことを学ぶのではなく、これまで学んだ内容を総復習することが大事です。また、試験当日に万全の体調で臨むため、十分な睡眠をとるよう心がけましょう。
宅建独学に役立つおすすめ教材と参考書3選
評判の高い教材の紹介
- 『みんなが欲しかった! 宅建士の教科書』
- 『スッキリわかる宅建士』
- 『2025年版 宅建士 実践講座』
これらの教材は、多くの独学者に支持されています。それぞれの教材は特徴が異なるため、自分に合ったものを選ぶことが重要です。
本を選ぶときは、見やすさやわかりやすさを重視しましょう。それぞれのテキストの詳細な比較は改めていたします。
おすすめのYoutube3選
- 「棚田行政書士の不動産大学」
- 「ゆーき大学」
- 「宅建吉野塾」
それぞれの詳細な解説は改めていたします。
通信、予備校おすすめ3選
ではここからは通信、予備校について解説していきます。
- スタディング
- 資格の学校TAC
- LEC東京リーガルマインド
それぞれ詳しくは改めて解説します。
勉強が「きつい」ときは?
勉強が大変に感じたときは、以下の方法で乗り越えましょう。
- 小さな目標を作る: 毎日1時間やる、など。
- 休憩を取る: 疲れたら少し休む。
- 仲間を作る: 勉強仲間と励まし合う。
無理せず、少しずつ進めることが大切です。
試験に落ちたらどうする?
失敗する理由としては、
- 勉強時間が足りなかった。
- 過去問をあまり解かなかった。
- スケジュール通りに進められなかった。
次に挑戦するときは、これらを改善し、過去問をたくさん解きましょう。
まとめ
宅建を独学や通信講座で合格するには、計画的に進めることが大切です。その計画をするにあたり、何が自分に合っているのかをしっかりと比較すること必要です。
資格を取ることで、将来の選択肢が広がります。ぜひ、挑戦してみてください!
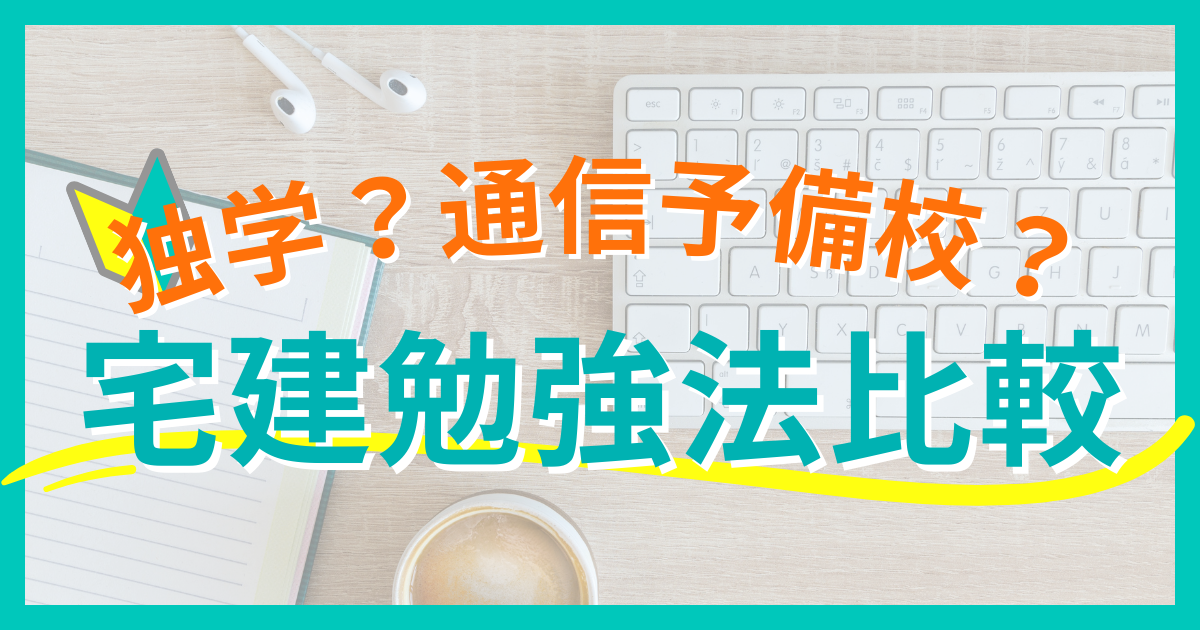


コメント